1月に和菓子店に並ぶ、白くふっくらとした形の「花びら餅」。
お餅からニョキッと出ている棒のようなもの、何だと思いますか?
なんと、ごぼうなんです!
お菓子にごぼう?!と思わず目を疑いたくなるようなお菓子ですが、
この組み合わせ、不思議と美味しいんですよね~!!
平安時代の料理がルーツというから驚きです。その由来を調べてみました。
花びら餅の由来は?
気になる花びら餅の由来ですが、なんと平安時代までさかのぼります!
そのころ、宮中で長寿を願う新年の「歯固め」の儀式に、大根や猪、押鮎(=古来、新年の祝いに用いていた塩漬けにした鮎)などを食べる習わしがあって、
江戸時代にそれに似せて作られたお菓子が広まったのが、のちの「花びら餅」の原形なのだそう。
気になるごぼうは、押鮎に見立てておかれたものだそうですよ。
土の中にしっかり根を張るので「家の基礎がしっかりしている」ことや「長寿」を願う意味が込められていて、おせちのお煮しめなどにも使われている縁起のいい根菜ですよね~。
甘煮にしてみそ餡に合わせると、なんとも言えない美味しさで、お腹も大満足ですね!
花びら餅は、なんと雑煮に見立てられた和菓子だった!
「花びら餅」は、やわらかな白い餅を薄く広げて、上品な甘さのみそ餡をのせ、
甘煮にしたごぼうを2本、そしてひし餅を模したにんじんの羊羹を重ねます。
餅、みそ、ごぼう、にんじん、この組み合わせは、まさしくお雑煮の見立てなんですね!
このように歴史の長い花びら餅ですが、明治時代に裏千家十一代家元玄々斎が初釜で使うことを許可され、新年のお菓子として、全国の和菓子屋でも作られるようになりました。
関西でもお正月では神戸などでもふつうにお店に並んでいます(^-^)
お菓子やさんによって、少しずつ違っていて、何個か食べ比べてみたいな~と迷ってしまいますが、1つ食べればお腹いっぱいになるボリュームなのがうれしいやら悲しいやら(笑)
花びら餅 まとめ

花びら餅の歴史もさることながら、雑煮だったのにはびっくりでしたね!
私は毎年、近くの神社の初釜で花びら餅をいただきますが、これ一つで甘さとしょっぱさ、そしてお餅でお腹がとても満たされます(^-^)
是非みなさんも食べてみてくださいね。




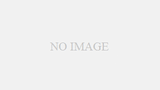

コメント